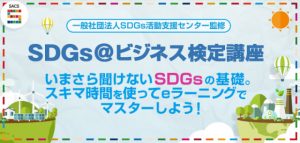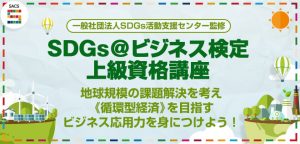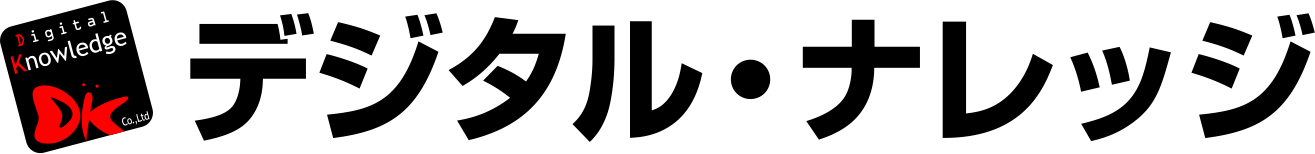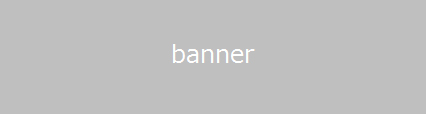【中学生向け】今すぐ始められる!SDGsをテーマにした自由研究アイデア集

夏休みの自由研究のテーマで悩んでいませんか?
SDGs(持続可能な開発目標)をテーマに選べば、身近な問題を通じて世界の課題に向き合うことができ、学びも発表も充実します。この記事では「SDGsとは何か」「なぜ自由研究に向いているのか」「具体的なテーマ例5選」などを分かりやすく解説します。中学生や保護者・先生の皆さんにも安心して取り組めるよう、書き方やまとめ方のコツも紹介。未来を見つめる自由研究を、一緒に楽しんで始めましょう!
・夏休みの自由研究に悩んでいる中学生
・SDGsについて興味がある中学生
・中学生のお子さんを持つ保護者の方
目次
なぜ今、中学生の自由研究にSDGsがおすすめなのか?

SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年に国連が定めた「持続可能な開発目標」で、2030年までに達成すべき17の目標があります。
SDGsは世界全体の目標でありながら、中学生が身近な題材を通じて「社会」「環境」「経済」といった多様な分野を学ぶことができる点で、自由研究にぴったりです
さらに、探究的な視点から自分なりのテーマを選び、実験・観察・調査を組み立てられる柔軟さも魅力。学校や社会でSDGsへの関心が高まっている今こそ、自分の興味と社会の課題を結びつける絶好のチャンスです。
SDGsとは?中学生にもわかりやすく解説
SDGsは「地球上の誰一人取り残さない」ことを目指し、2030年までに達成すべき目標が17項目、具体的なターゲットは169もあります。例えば「貧困をなくそう」「海の豊かさを守ろう」など、身近な生活からでも考えられるテーマが多く、中学生にも理解しやすい構成です。
学校の授業やニュース、SNSでも目にする機会が増えているため、“世界の課題”というと難しく感じがちですが、自由研究のテーマとして身近な課題から探せば、自然に学びにつながります。
学校や社会でSDGsが注目されている背景
近年、学校では教育指導要領にSDGsの視点が導入され、授業や課題にも取り入れられることが増えています。加えて、報道や企業、自治体などでもSDGsへの取り組みが進んでおり、自由研究を通じて社会課題に関心を持つことは、生徒の学びの視野を広げる機会につながります。
さらに、発表時にSDGsで学んだ視点を共有することは、クラスや地域の中でも共感を呼びやすく、「SDGsに興味がある人」として評価につながる可能性もあります。
SDGsをテーマにした自由研究の進め方

SDGsをテーマに自由研究を行う場合、まず大切なのは「自分の興味に合った目標」を見つけることです。SDGsの17の目標には、環境、貧困、教育、ジェンダーなど幅広い分野があり、自分の身近な疑問や体験から出発するのが成功のポイントです。
次に情報収集。ネットや本、身の回りのデータを活用し、課題を深掘りしましょう。観察やインタビュー、簡単な実験など、調査の方法を工夫すると、よりオリジナリティのある研究になります。
最後にまとめと発表。グラフや写真を取り入れて視覚的に伝えると、聞き手の印象にも残ります。
研究テーマの決め方(17目標から選ぶ)
まずはSDGsの17の目標をざっと見て、自分の興味がある分野を選びましょう。たとえば、動物が好きなら「陸の豊かさを守ろう」、水に興味がある好きなら「安全な水とトイレを世界中に」が関連します。自分の生活に関わるテーマを見つけるのがコツです。
学校の授業や新聞で目にしたこと、日常生活で感じた「なぜ?」を出発点にすれば、自然と研究が進めやすくなります。
情報収集と調べ方のポイント
テーマを決めたら、図書館やインターネットを使って情報を集めましょう。信頼できるサイト(国連広報センター、官公庁など)を使うことが大切です。
また、家族にインタビューしたり、実際にゴミの量を記録したりと、自分で調べる方法を組み合わせると説得力が増します。調べたことはノートや表、写真などで整理すると、後でまとめるときに役立ちます。
まとめ方と発表の工夫
研究のまとめでは、「目的」「調べたこと」「方法」「結果」「考察」の順に構成するとわかりやすくなります。
表やグラフ、写真を使うことで視覚的にも伝わりやすくなります。発表のときには、「なぜこのテーマにしたか」「調べて気づいたこと」「自分の考え」をしっかり伝えると、聞き手の共感を得られます。SDGsのマークや17の目標アイコンを使うのも、視覚的にインパクトがありおすすめです。
中学生におすすめのSDGs自由研究テーマ5選

SDGsには17の目標がありますが、中学生の自由研究では「自分の生活に身近なテーマ」を選ぶことがポイントです。ここでは、調査・実験・観察がしやすく、学びやすいおすすめのテーマを5つ厳選してご紹介します。どれも環境や社会に関心を持ちやすく、発表でも注目されやすい題材ばかりです。それぞれに必要な準備や進め方のヒントも添えているので、自分の興味に合ったテーマからチャレンジしてみましょう。
環境問題を調べてみよう(例:プラスチックごみ)
 【関連目標】目標14「海の豊かさを守ろう」
【関連目標】目標14「海の豊かさを守ろう」
海に流れ込むプラスチックごみは、生き物に深刻な影響を与えています。
自由研究では、自宅で出るプラごみを1週間記録し、どんな種類が多いのかをグラフにまとめる方法があります。また、リサイクルマークの意味やごみの分別ルールを調べ、地域のリサイクル事情と比較するのも学びになります。回収ボックスのある店舗を調べて地図にまとめるなど、発表形式も工夫できます。
身近な食品ロスを調査(例:家庭の食品廃棄量)
 【関連目標】目標12「つくる責任 つかう責任」
【関連目標】目標12「つくる責任 つかう責任」
家庭でどれだけ食べ物が無駄になっているか、実際に記録してみましょう。
冷蔵庫の中の食品チェックや、残飯の重さを量ることで、食品ロスの実態が見えてきます。賞味期限の誤解、買いすぎ、食べ残しなど、原因を分析してポスター形式でまとめるのもおすすめです。家族で協力して改善案を考え、実践してみると変化が出てさらに面白くなります。
水の大切さを実感(例:水の使用量を記録)
 【関連目標】目標6「安全な水とトイレを世界中に」
【関連目標】目標6「安全な水とトイレを世界中に」
水道の使用量を記録し、どの行動でどれだけ水を使っているかを調べる実験です。
洗顔、歯磨き、シャワーなど、1日単位で記録をとり、節水を意識した行動と比較してみましょう。さらに世界の水事情と比較すれば、日常生活の中で「水を当たり前に使えること」のありがたさが実感できます。節水グッズの活用効果を実験してみるのもおもしろい視点です。
ジェンダー平等って何?(例:家事分担を調査)
 【関連目標】目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
【関連目標】目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
家族の中で、誰がどんな家事をしているかを記録し、家事分担のバランスを分析する研究です。
性別による役割意識や、家族内での「当たり前」に気づくきっかけになります。また、友達の家や学校の先生にアンケートを取れば、比較分析もできます。「自分たちにできることは何か?」を考えて提案までつなげると、発表に深みが出ます。
フェアトレード商品を調べる(例:チョコレートの裏側)
![]() 【関連目標】目標1「貧困をなくそう」、目標8「働きがいも経済成長も」
【関連目標】目標1「貧困をなくそう」、目標8「働きがいも経済成長も」
フェアトレードは、開発途上国の人々に正当な報酬を支払う仕組みです。
チョコレートやコーヒー、バナナなどのフェアトレード商品を実際に探して購入し、ラベルや原産国、価格などを調べてみましょう。また、通常の商品と比較し、どんな違いがあるか、買い物が社会貢献につながることを学ぶことができます。スーパーやオンラインで商品を調査するのもおすすめです。
SDGs自由研究を成功させるコツ

SDGsをテーマにした自由研究を充実させるには、「興味のあること」「身近にあること」から始めるのが最大のポイントです。
内容が難しそうに感じる場合もありますが、実際は日常生活の中にヒントがたくさん隠れています。また、観察や実験を取り入れることで、よりリアルな学びが得られ、発表の際も説得力が増します。さらに、自分だけのオリジナル視点を加えることで、他の人と差がつく印象的な研究になります。身の回りに目を向け、自分なりの問いと答えを探求する姿勢が、成功へのカギです。
テーマは「身近」「興味あること」を選ぶ
SDGsは地球規模の目標ですが、自由研究では「自分の生活に関係すること」をテーマにするのがおすすめです。
たとえば、ゴミや水、買い物など、毎日関わっていることから出発すれば、無理なく研究を深められます。また、「なんでこうなるの?」「もっと良くするには?」という疑問を出発点にすることで、自分だけの切り口が見つかります。難しそうに見えるテーマも、身近な視点から考えると取り組みやすくなります。
実験や観察を取り入れてみる
観察や記録、簡単な実験を取り入れると、研究に具体性が生まれます。
たとえば、ごみの量の変化を記録したり、水使用量のビフォー・アフターを比較したりすることで、数字として結果が見えるようになります。また、日記形式で毎日の変化を記録するのもおすすめです。実験といっても大がかりなものでなく、家庭の中でできる範囲で十分。五感を使った観察や体験が、深い気づきにつながります。
オリジナルの視点を加えて発表しよう
自由研究の発表では、「自分だけの視点」が大きなポイントになります。
単に調べたことをまとめるだけでなく、「自分はどう考えたか」「今後どうしたいか」など、自分の意見や提案を加えることで、より印象的になります。また、SDGsの17目標との関係を明確に示すことで、聞き手に伝わりやすくなります。色使いやレイアウトにも工夫を加えることで、視覚的にも伝わる発表が可能です。
まとめ|SDGsで未来を考える自由研究をしよう
SDGsは一見難しそうに見えますが、自分の身近なことと結びつけて考えることで、楽しく、深く学べるテーマになります。
自由研究でSDGsを選ぶことで、「知る」「考える」「行動する」という一連の学びの流れを自然に体験できるのです。また、将来に向けた意識を育む絶好のチャンスでもあります。今回紹介したテーマ例や進め方を参考に、自分らしい研究を進めてください。そして、研究を通じて得た気づきを周囲に伝えることで、SDGsの輪が広がっていくでしょう。
自由研究が、未来を変える第一歩になるかもしれません。
夏休みにSDGsがテーマの映画を観るのもおすすめですよ!
➡ 【関連記事】SDGsを映画で学ぼう!SDGs関連がテーマのフィクション・ドラマ映画6選
➡ 【関連記事】SDGsを映画で学ぼう!SDGs関連がテーマのドキュメンタリー映画5選
➡ 【関連記事】SDGsを映画で学ぼう!海と陸の動物保護がテーマの映画4選
もっと学びたい方へ
割引クーポンプレゼント!
感想をお寄せくださった方全員に、「SDGs@ビジネス検定講座」「SDGs@ビジネス検定上級資格講座」の10%割引クーポンプレゼント実施中。
「SDGs@ビジネス検定講座」はSDGsを基礎から学びたい中学生にも最適な講座です。
クーポン対象講座
編集者情報
 |
株式会社デジタル・ナレッジ サービス推進事業部 事業部長 野原 成幸 |
| わからないことはインターネットで検索していた時代から、AIに質問することでさらにスピーディーに解決できる時代になりました。多くの場合、解決して終わりだと思いますが、「これについてもっと知りたいな」「学んでみたいな」ということも少なからずあるのではないでしょうか。 Pre.STUDYでは、何かを学びたいと思って検索する人にとっての学びの予習(prestudy)になり、明日誰かに話したくなる情報を発信しています。それと同時に、なんとなく湧いた疑問を検索した先で、ふと芽生えた知的好奇心をくすぐり、学びのきっかけになるメディアを目指しています。 | |