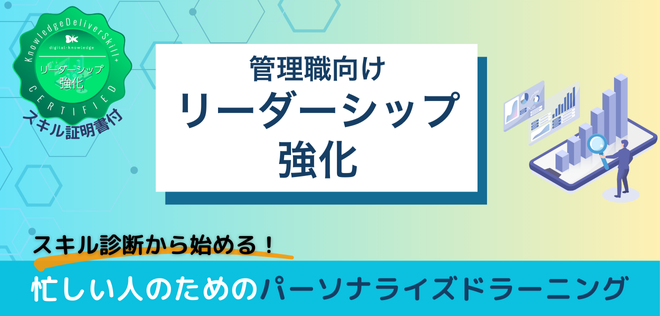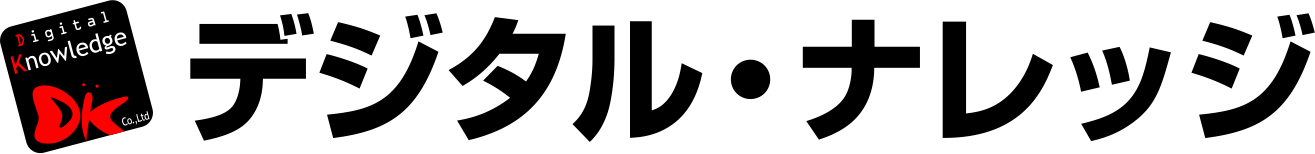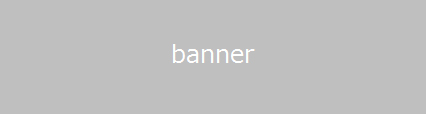管理職に求められるリーダーシップとは?ビジョンの伝え方と育成法

「優秀な人ほど、管理職になると悩み始める」
これは多くの企業で見られる現象です。
これまで個人のスキルで成果を出してきたプレイヤーが、チームを率いる立場になると、突然“成果が出せない人”のように見える。なぜでしょうか?
そのカギとなるのが“リーダーシップ”です。
しかし一口にリーダーシップと言っても、管理職に求められるそれは単なる「引っ張る力」ではありません。「ビジョンを描き、部下を育て、組織を導く力」としてのリーダーシップが、今まさに問われているのです。
本記事では、管理職や管理職候補者に向けて、
- 今なぜ“リーダー型管理職”が必要なのか
- どんなリーダー像が望ましいのか
- 実際に部下にビジョンを伝え、育てるにはどうすべきか
を体系的に解説します。
・育成やマネジメントに不安を感じている主任・係長クラス
・チームの停滞感に悩む管理職候補者
・リーダーシップの正解が分からず戸惑う30代中堅層
目次
プレイヤー型管理職から“リーダー型管理職”への転換が求められている理由
これまでの管理職像と今求められる役割のギャップ
これまでの管理職は、「部下の業務を管理し、自らも現場で成果を出すプレイングマネージャー」としての役割が重視されてきました。
しかし、目の前のタスクに追われるだけでは、チーム全体の成長や戦略的な動きは見えてきません。
今、求められているのは“業務遂行の延長”ではなく、「人と組織を導く存在」への進化です。
部下の多様化とエンゲージメントの低下
現代の職場では、価値観・働き方・キャリア観が多様化しています。
一昔前のように「上司の言うことを聞いていれば昇進できる」といったモデルは機能しません。
若手・中堅の多くは、“意義”や“納得感”を重視して働いており、そうした部下に対しては、「何をやれ」ではなく「なぜやるのか」を示すリーダーシップが求められます。
経営と現場をつなぐ“橋渡し役”としての期待
管理職は「経営」と「現場」をつなぐ中間ポジションです。
経営戦略を現場に浸透させ、現場の声を経営に伝える。
この“翻訳力”と“橋渡し力”が、管理職の影響力の本質であり、それを発揮するには単なる管理業務ではなく、ビジョンを語り人を動かす力が不可欠です。
自律型組織への転換とリーダーの再定義
リモートワーク、成果主義、プロジェクト型組織の浸透などにより、これからの組織は「自律」が前提になっていきます。
細かく指示を出すマネジメントはむしろ逆効果になるケースも。
だからこそ、「任せる力」や「対話で導く力」こそが新時代のリーダーシップなのです。
管理職が発揮すべきリーダーシップのタイプとは

リーダーシップとマネジメントの違いを理解する
まず押さえたいのは、リーダーシップとマネジメントは同じではないということ。
マネジメントは「計画・管理・運営」にフォーカスし、リーダーシップは「人と組織を動かす力」です。どちらか一方では不十分で、両輪としてバランスよく発揮することが重要です。
ビジョン型リーダーシップの本質とは
今、最も求められているのは「ビジョン型」のリーダーシップです。
チームに「私たちはどこに向かっているのか」「なぜこの仕事をするのか」を示すことで、メンバーの主体性や納得感を高めます。強制ではなく共感で動かす力がポイントです。
サーバント型リーダーシップの重要性
「支える」リーダーも、現代では欠かせません。
サーバント型リーダーシップは、部下を導くのではなく、部下の成長を支援するスタイル。傾聴や共感のスキルが重要であり、信頼の土壌づくりにも直結します。
状況に応じて柔軟に対応する“シチュエーショナルリーダー”
部下の能力や意欲、タスクの難易度によって、最適な関わり方は変わります。
指示すべき時もあれば、任せて見守るべき時もある。状況に応じてスタイルを切り替える柔軟性が、真のリーダーには求められています。
ビジョンを伝える力をどう高めるか

自分の価値観と信念を明確にする
ビジョンを語るには、まず自分自身の軸が必要です。
「自分は何のためにこの組織にいるのか」「どういう未来をつくりたいのか」といった問いに答えられないと、言葉が上滑りしてしまいます。リーダーの“在り方”が伝達力を支えます。
組織の方向性を具体的に言語化する
「成長しよう」「貢献しよう」といった抽象的な表現だけではメンバーは動きません。
組織のビジョンを“行動レベル”にまで落とし込むことで、メンバーが「自分ごと」として捉えるようになります。
チームへの浸透方法を工夫する
ビジョンは“掲げて終わり”ではなく、“浸透して初めて意味がある”もの。
全体会議や1on1で繰り返し語る、ストーリーで伝える、共通言語として活用するなど、地道な働きかけが必要です。
日常業務との接続で「使えるビジョン」へ
ビジョンを業務や評価基準にリンクさせると、メンバーは行動の指針として自然に活用するようになります。
例えば「この施策は、私たちのビジョンにどう貢献しているのか?」という問いをチーム内で投げかける習慣をつけましょう。
部下を主体的に育てるコミュニケーション術

信頼がすべてのスタート地点
育成の前提は「この人になら話したい」と思ってもらえる信頼関係です。
部下の話に耳を傾け、過去の努力を認め、小さな変化にも気づく。それだけで関係性は大きく変わります。
ティーチングとコーチングを使い分ける
スキルを教える場面ではティーチング、考えさせたい場面ではコーチング。
この使い分けができると、部下の思考力と主体性が飛躍的に伸びます。
問いを活用した“考える力”の支援
「どう思う?」「あなたならどうする?」という問いは、部下を自律的にします。
正解を与えるのではなく、考える機会を与える。これが育成のコアです。
任せて育てる“手放す勇気”
任せることはリスクではなく、信頼の表現。
アサインする際は「目的」「期待する成果」「判断の軸」を丁寧に伝えることで、任される側も安心して動けます。
失敗の経験を“成長の糧”に変える
部下が失敗したときに、責めるのではなく「そこから何を学んだか?」を一緒に考えることが大切です。
このプロセスが、部下を“任せられる人材”へと導きます。
まとめ|管理職のリーダーシップは“未来をつくる力”
管理職に求められるリーダーシップとは、単なる「指示命令」や「業務の管理」ではありません。
それは、チームに未来のビジョンを示し、部下を信じて任せ、共に成長しながら組織を前進させる力です。
そのためには、自らの価値観を明確にし、対話を通じてチームとビジョンを共有し、日々のコミュニケーションの中で信頼関係を築いていくことが不可欠です。
リーダーとは、“完璧な人”ではなく、“学びながら前進し続ける人”。迷い、悩み、試行錯誤する姿こそが、チームに影響を与えるリーダーの在り方です。
「自分にリーダーシップがあるだろうか」と不安に感じる方こそ、すでに第一歩を踏み出しています。
なぜなら、問い続ける姿勢こそが、リーダーとしての本質だからです。
あなたの言葉が、誰かの背中を押す力になります。
あなたのビジョンが、チームの未来をつくるきっかけになります。
リーダーシップは、今この瞬間から育てていくもの。
あなたらしい“未来をつくる力”を、今日から少しずつ形にしていきましょう。
もっと学びたい方へ|割引クーポンプレゼント!
感想をお寄せくださった方全員に、N-Academy「管理職向けリーダーシップ強化」の10%割引クーポンプレゼント実施中。
クーポン対象講座
編集者情報
 |
株式会社デジタル・ナレッジ サービス推進事業部 事業部長 野原 成幸 |
| わからないことはインターネットで検索していた時代から、AIに質問することでさらにスピーディーに解決できる時代になりました。多くの場合、解決して終わりだと思いますが、「これについてもっと知りたいな」「学んでみたいな」ということも少なからずあるのではないでしょうか。 Pre.STUDYでは、何かを学びたいと思って検索する人にとっての学びの予習(prestudy)になり、明日誰かに話したくなる情報を発信しています。それと同時に、なんとなく湧いた疑問を検索した先で、ふと芽生えた知的好奇心をくすぐり、学びのきっかけになるメディアを目指しています。 | |