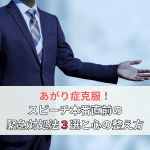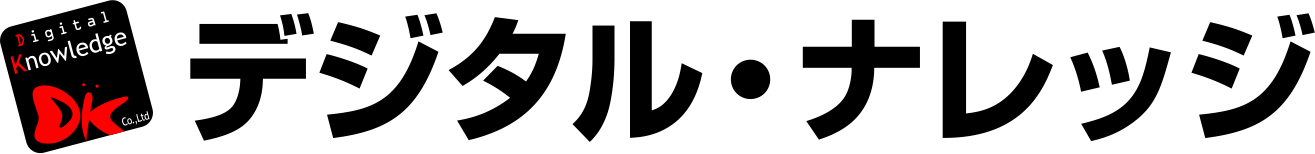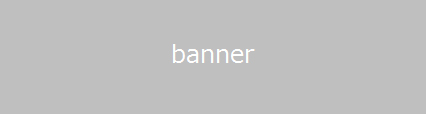デジタルマーケティングの設計図 KGI/KPI設定とチャネル戦略の全体像
【連載第6回|初心者向けデジタルマーケティング入門】

SNS投稿、広告出稿、ブログ執筆。デジタルマーケティング担当者は、日々忙しいタスクに追われます。でも、「私たちはどこへ向かっているのか?」「この施策は本当に事業に貢献しているか?」と問われたら、明確に答えられますか?
多くのマーケターが感じるこのモヤモヤを解消するのが、本連載の目的です。これから6回にわたり、初心者向けにマーケティングのフレームワークを解説します。第1回は、KGI/KPIとチャネルの全体像。KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)はビジネス全体の最終目標、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)はその進捗を測る中間指標、チャネルはこれらを実現する手段(SEO、広告、SNSなど)です。
このフレームワークで、断片的な活動を一貫した戦略に変えましょう。日々のタスクが最終目標(KGI)の達成にどう貢献しているかを常に意識することで、施策の優先順位が明確になり、無駄な作業を減らせます。作業者から戦略家へ進化する第一歩です。
株式会社吉和の森
代表取締役 森 和吉(もり・かずよし)
https://yoshikazunomori.com/
ウェブ解析士マスター、チーフSNSマネージャー
「キャリア公式サイト」「広告サイト」など、アライアンスを中心とした50以上の月額公式サイト、100万人以上が利用するサイト、100以上のコンテンツの立ち上げ、集客化に成功。1日の売り上げが1億以上のソーシャルゲーム、カジュアルゲームの制作に携わるなど、さまざまな業態・業種にデジタル・マーケティングを取り入れ、企業に追い風を起こし続けている。
・施策の効果に不安のあるデジタルマーケティング担当者
・デジタルマーケティングで効果をあげたいサービス担当者
なぜ目標設定が最重要なのか KGIとKPIを理解する
曖昧な願いから具体的な目標へ KGIの力
マーケティングの土台はKGI設定です。KGIは、期間内に達成すべき重要な成果を、具体的・測定可能な数値で定義します。例えば、「売上を増やす」ではなく、「ECサイトの売上を年度末までに前年比15%増加させる」のように設定します。
このように目標を具体化する際に役立つのが、「SMART」というフレームワークです。
- Specific:具体的に(例:ECサイトの売上)
- Measurable:測定可能か(例:前年比15%増)
- Achievable:達成可能か(現実的な目標か)
- Relevant:事業目標と関連しているか(経営戦略と一致しているか)
- Time-bound:期限があるか(例:年度末までに)
実例:ECサイト運営者のKGI設定
ある中小ECサイトのオーナーが、美容グッズを扱っています。曖昧な「売上アップ」からスタートし、SMARTで具体化すると、「2025年度末までに、スキンケア商品の月間売上を前年比20%増加させる(現在月500万円→600万円)」となります。これを経営陣と共有し、営業目標(新規顧客20%増)と連動させました。結果、マーケティング予算をスキンケアカテゴリに集中でき、事業全体の成長に直結しました。
KGIは売上高、利益、成約件数など事業の根幹となる指標です。設定時は、経営層や営業との対話が鍵となります。部門間の目標をすり合わせ、成功の定義を共有することで、マーケティングが事業成長に直結します。
プロセスの進捗を測る KPIの定義
KGIが定まったら、KPIで道筋を測ります。KPIはKGI達成のための中間目標で、マーケターが影響を与えられる指標です。例えば、KGI「月間売上1,000万円」なら、KPIは「訪問者数」「購入率(CVR、Conversion Rate)」「平均顧客単価」といった指標になります。
KPIの力は二つあります。一つは、KGI達成の可能性を予測する「先行指標」としての役割。もう一つは、問題発生時の診断ツールとしての役割です。
訪問者数は目標を達成しているのに購入率が低い場合、ボトルネックを特定し、早期に修正が可能です。例えば、「サイトのデザインが分かりにくい」「商品情報が不足している」といった仮説を立て、A/Bテストやサイト改修といった具体的なアクションに繋げられます。KPIは進捗を追跡するだけでなく、戦略を調整するためのツールなのです。
分解の技術 KPIツリーで目標と行動を結びつける
KPIツリーとは?一つの大きな目標を、多数の小さなレバーへ
KPIツリーは、KGIを頂点に、数式やロジックで階層的に分解した樹形図です。抽象的な目標を、現場の具体的なアクションに落とし込むために使います。「なぜ」ではなく「どのように達成するか」を問いかけながら分解していくのがポイントです。例えば、「売上」は「アクセス数 × 購入率 × 顧客単価」のように分解できます。
作成プロセスで論理を整理することで、売上に直接繋がらない「いいね!の数」や「フォロワー数」といった見た目の数字(実際の成果に直結しない見かけ上の数字)に惑わされるのを防ぎ、データに基づいた戦略立案を促します。
実践例 ECサイトのKPIツリーを構築する
ECサイトを例に解説します。
<ECサイトのKPIツリー>
レベル0(KGI):3ヶ月後の月商2,000万円(現在1,500万円)
レベル1:売上 = 訪問者数 × 購入率(CVR) × 平均顧客単価(AOV)
レベル2:
▽訪問者数 = 自然検索流入数 + 広告流入数 + SNS流入数 + メルマガ流入数 (例:全体の訪問者数目標を達成するため、各チャネルの特性に応じて「自然検索から15万人」「広告から10万人」のように目標値を設定)
▽購入率(CVR) = カート投入率 × 購入完了率(目標:投入率5%、完了率80%)
▽平均顧客単価(AOV, Average Order Value) = 平均購入商品数 × 1商品あたり平均金額(目標:1回の購入で2商品、1商品あたり5,000円)
<チーム分担>
SEOチーム:「自然検索流入数10万人」を目指しキーワード調査を実施
広告チーム:「広告流入数10万人」を達成するためにwebで展開している広告を最適化
<結果>
1ヶ月目で訪問者数が前月比20%増え、KGI達成の軌道に乗った。
このように、大きな目標が、チームごとの具体的なアクション(例: SEO担当は自然検索流入数を増やす、広告担当は広告流入数を増やす、サイト改善担当はカート投入率を上げる)に変わります。
他のビジネスモデルへの応用
KPIツリーは普遍的なフレームワークです。ビジネスモデルの収益構造に合わせて分解することが重要です。
例:
| ビジネスモデル | 代表的なKGI(例) | 主要なレベル1 KPI | 主要なレベル2 KPI |
|---|---|---|---|
| Eコマース | 月間売上300万円 | セッション数、購入率(CVR)、顧客単価 | 自然検索流入数、広告クリック数、カート投入率 |
| BtoBリードジェネレーション | 月間有効リード50件 | 総リード獲得数、リードの質(有効率) | ホワイトペーパーDL数、フォーム送信率、MQL転換率 |
| メディア/コンテンツサイト | 月間広告収益100万円 | PV数、1PVあたり収益 | UU数(ユニークユーザー数)、1訪問あたりPV数、広告クリック率(CTR) |
自社のビジネスモデルに合わせて、ぜひ分解を試してみてください。
指標から行動へ デジタルマーケティングチャネルの生態系を俯瞰する
KPIとチャネルの連携 適切な仕事に、適切な道具を
KPIツリーで具体的な行動指標(レバー)を特定したら、次はその指標を動かすためのチャネルを選択します。「自然検索でのセッションを増やしたい」ならSEO、「広告の顧客獲得単価を下げたい」ならリスティング広告の改善、といった具合です。流行っているからという理由で「TikTokを始めよう」と安易に飛びつく「チャネルファースト」は危険です。目的(KGI/KPI)が曖昧なままでは、投下したリソースが無駄になったり、効果測定ができずに次に繋がらなかったりするためです。
常にKGI/KPIから逆算する「ゴールファースト」で考え、費用対効果の高いチャネルを選びましょう。
3つの主要チャネルタイプとその役割
チャネルは大きく3つのタイプに分類でき、これらを連携させることでエコシステムを形成します。
• オウンドメディア(ウェブサイト/ブログ、SEO)
役割:マーケティング活動の中心拠点。信頼構築とコンバージョン(購入や問い合わせ)の受け皿となります。
特性:一度作成したコンテンツが資産として蓄積される「ストック型」。良質なコンテンツは長期的に集客し続ける力を持ちます。
主要KPI:自然検索セッション、滞在時間、CVR。
• ペイドメディア(Google広告、SNS広告)
役割:短期的な集客や、特定のターゲットへの即時リーチを担います。
特性:費用をかければすぐに始められ、効果測定がしやすいのが特徴です。ただし、広告を止めると露出も止まってしまいます。
主要KPI:CPA(顧客獲得単価)、ROAS(広告費用対効果)、CTR(クリック率)。
• アーンドメディア/ソーシャルメディア(SNS、プレスリリースなど)
役割:ユーザーとの接点創出と、口コミや評判など第三者による情報の拡散を担います。
特性:投稿や情報発信そのものは無料ですが、信頼や共感を得るまでに時間がかかります。情報の拡散力が高い「フロー型」で、瞬間的な話題性は高いですが情報が流れやすい側面もあります。
主要KPI:エンゲージメント率、リーチ数、クリック数。
顧客はこれらのチャネルを横断して、購入などの意思決定を行います(例:広告で認知→SNSで情報収集→公式サイトで購入)。
実例:美容ブランドの連携フロー
20代女性向けスキンケアブランドの場合、まずペイドメディアであるInstagram広告で新商品を認知させます(リーチ数10万人)。興味を持ったユーザーがSNSで口コミをチェックし(エンゲージメント率5%)、信頼を深めます。そして、オウンドメディアのブログで詳細なレビュー記事を読み、公式サイトでの購入に至ります(CVR 3%)。
この一連の流れで、KGIである「月間売上20%増」を達成しました。このように、チャネルを連携させて設計することで、優れた顧客体験を創出し、KGI達成へと繋げることができるのです。
計画を基に、実行へ移す
今回の学びを3ステップでまとめます。
- KGI設定:関係者と合意の上で、具体的で測定可能なゴールを決める。
- KPIツリー作成:KGIを論理的に分解し、日々の活動に繋がる実行指標(KPI)に落とし込む。
- チャネル実行:各KPIを達成するために最適なチャネルを選択し、連携させて施策を実行する。
このフレームワークは、単なる計画ツールではありません。「なぜこのタスクを行うのか」が常に明確になり、多忙な業務を目的ある活動に変え、データに基づいた意思決定を可能にする「思考の羅針盤」です。
次回、第2回は顧客理解を深めるための「3C/STP/カスタマージャーニー」について解説します。施策に説得力を持たせるために欠かせない視点です。ご期待ください。
もっと学びたい方へ|関連書籍
 著者:森 和吉
著者:森 和吉
出版社:ぱる出版
発売日:2022年12月22日
価格:¥1,650(税込)
商品URL:https://amzn.asia/d/0t37EZr
編集者情報
 |
株式会社デジタル・ナレッジ サービス推進事業部 事業部長 野原 成幸 |
| わからないことはインターネットで検索していた時代から、AIに質問することでさらにスピーディーに解決できる時代になりました。多くの場合、解決して終わりだと思いますが、「これについてもっと知りたいな」「学んでみたいな」ということも少なからずあるのではないでしょうか。 Pre.STUDYでは、何かを学びたいと思って検索する人にとっての学びの予習(prestudy)になり、明日誰かに話したくなる情報を発信しています。それと同時に、なんとなく湧いた疑問を検索した先で、ふと芽生えた知的好奇心をくすぐり、学びのきっかけになるメディアを目指しています。 | |