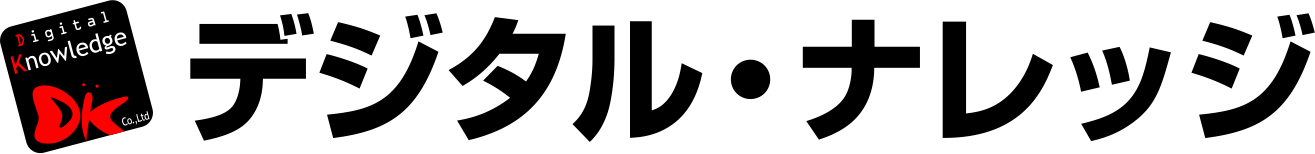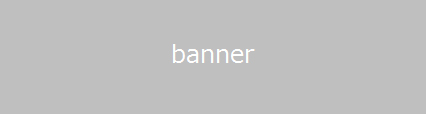【有価証券報告書の読み方】記載内容や初心者が見るべきポイントをわかりやすく解説
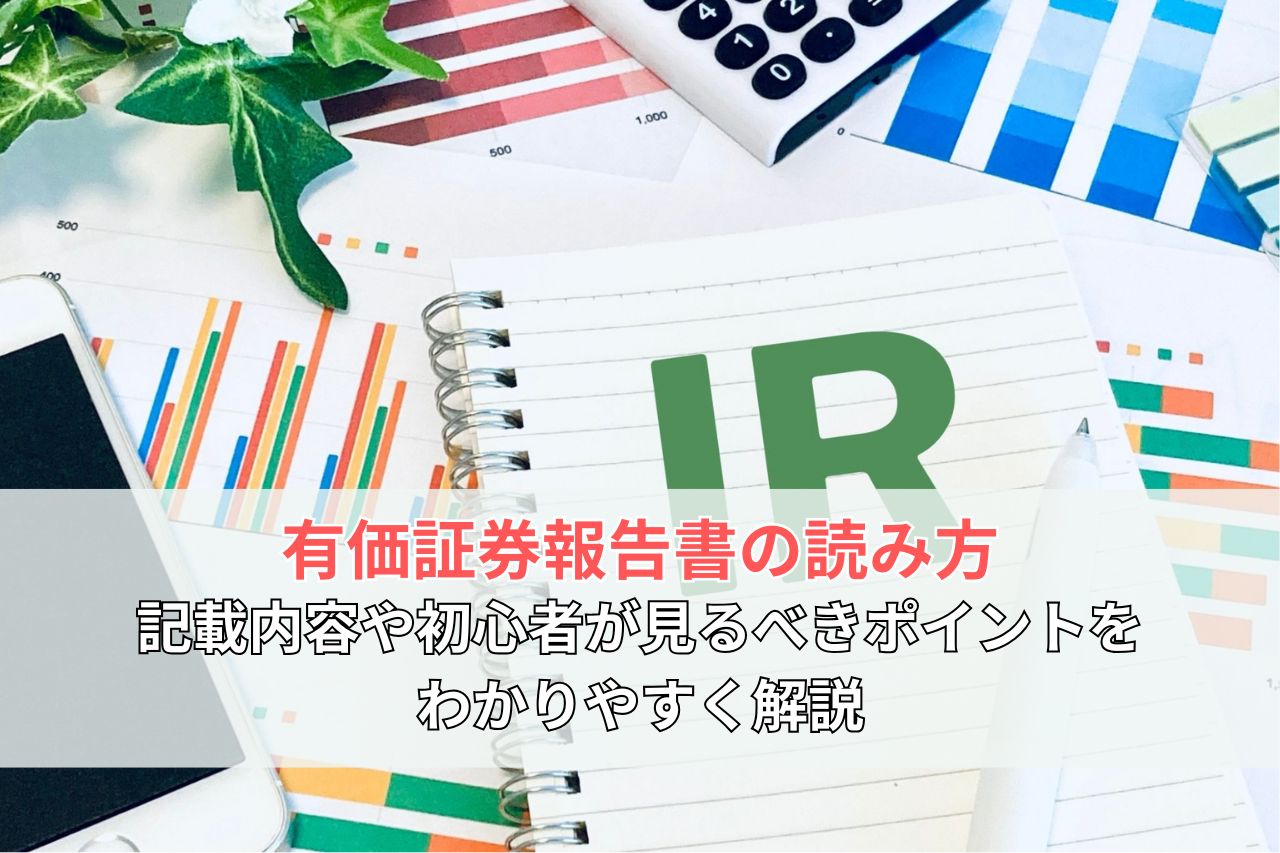
有価証券報告書は誰でも閲覧できる公開資料ですが、「ページ数が多すぎて読む気になれない」「そもそも何が書いてあるのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
じつは、有価証券報告書はすべてのページを読む必要はありません。ポイントを押さえれば、限られた情報だけでも十分に役立ちます。ただし、自分が知りたい情報を見極める知識が必要です。
この記事では、有価証券報告書の構成や注目すべきポイントを目的別にわかりやすく解説します。有価証券報告書をマスターすれば、投資や就活、ビジネスにおける営業活動に役立てることができます。情報収集で差をつけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
・有価証券報告書で企業の価値を具体的に分析し、投資判断したい投資中級者
・会社のありのままの姿を知り、他の学生と差をつけたい就活生
・顧客の経営状況や課題を知り、ビジネスチャンスを掴みたい法人営業担当者
目次
有価証券報告書って何が書かれているの?

有価証券報告書とは株式や債券を発行している企業が開示する、会社を客観視できる診断書のことです。有価証券報告書は金融商品取引法に基づき、作成と提出が義務付けられています。事業や経営の状態など、投資判断に有用な情報を外部の投資家へ適切に開示することが目的です。
有価証券報告書は事業年度ごとに発行され、インターネット上で自由に閲覧できます。業績の推移や財務状況、事業内容、将来の方針、人材構成など多角的な観点から会社の業績と将来の見込みが確認できます。多角的な観点から読み解くことは、投資家だけでなく就活生や営業担当者にもおすすめです。
有価証券報告書は、下記の3部構成になっています。
第二部「提出会社の保証会社等の情報」
監査報告書
第一部「企業情報」
有価証券報告書のメインは第一部で、全体の9割を占めます。
第一部の内訳は下記の7点です。
第2:事業の状況
第3:設備の状況
第4:提出会社の状況
第5:経理の状況
第6:提出会社の株式事務の概要
第7:提出会社の参考情報
有価証券報告書は200ページ以上になることもあり、すべてに目を通すには膨大な時間を要します。でも、全部を読む必要はないのでご安心ください。自分に必要な情報を選び取ることが大切です。見るべきポイントは次の章で解説します。
第二部「提出会社の保証会社等の情報」
第二部は有価証券の発行に保証会社が関連している場合に記載される情報です。ほとんどの上場企業には該当事項がなく、記載されないことが多いです。記載がある場合でも、企業の分析に直接関係がない情報なので、読み飛ばしても問題ありません。
監査報告書
監査報告書には公認会計士や監査法人による監査に関する情報が記載されています。有価証券報告書に記載された情報の正確性を第三者が証明しているため、情報の信頼性が高くなります。監査報告書にも直接的な企業の情報は記されていないため、目を通す程度で十分でしょう。
目的別:有価証券報告書の注目ポイント

ここでは、それぞれの立場に応じた有価証券報告書のチェックポイントについて解説します。
- 投資家が見るポイント
- 就活生が見るポイント
- 営業担当者が見るポイント
投資家が見るポイント
投資家が見るべきポイントは、企業の収益性、安全性、将来性に関する情報です。
収益性
第1【企業の概況】で過去5年間の収益の推移を確認します。売上高、経常利益、当期純利益などの項目において直近5年間で業績が伸びているか、赤字を計上していないかをチェックします。収益に大きな増減がないか、変化の跡や兆候がないかについても時系列で確認しましょう。
安全性
第1【企業の概況】で自己資本比率を確認しましょう。自己資本比率とは、企業の安定性を表す指標であり、純資産(返済義務のない資産)が総資産に占める割合を指します。自己資本比率が30〜40%の企業が目安となり、50%以上あれば安全性が高いです。
純資産の内訳は第5【経理の状況】の連結貸借対照表で確認できます。同業他社と比較して、十分な水準にあるか評価しましょう。
将来性
第2【事業の状況】で経営方針、経営環境及び対処すべき課題を確認します。【事業の状況】では今後の経営方針や企業が直面している課題が説明されています。決算書の数字だけでは読み取れない、経営者の考えやリスクに対する備えを確認しましょう。企業の目的やお客様への価値提供の内容を読み取ることで、企業の方向性が把握できます。
就活生が見るポイント
就活生が見るべきポイントは企業の実力と働く環境です。就活生にとって有価証券報告書は、企業の実情を知るために最良な資料です。有価証券報告書は公認会計士や監査法人による監査が入っているため、第三者目線での実力確認ができます。
客観的で信頼性の高い情報を読み取り企業研究を深めれば、他の学生と差をつけられます。
企業の実力
企業の実力は投資家が見るポイントと同様です。
働く環境
働く環境は第1【企業の概況】の第5【従業員の状況】で確認しましょう。従業員数、平均年間給与(平均年収)、平均年齢、平均勤続年数などの情報を同業他社と比較すれば、企業の特徴がわかります。創設時期や採用方針にもよりますが、平均勤続年数から離職率を予測できます。
「大企業だから大丈夫」などと過信せず、信頼できるデータから働く環境をイメージしましょう。
営業担当者が見るポイント
営業担当者が見るポイントは営業先の現状と経営上の課題です。有価証券報告書は見込み顧客(営業先)の課題を特定するためのリサーチツールとして活用できます。
営業先の現状
営業先の現状は、投資判断と同様に確認してください。
経営上の課題
経営上の課題は第2【事業の状況】と第3【設備の状況】で確認しましょう。
【事業の状況】は、投資判断における将来性の確認と同様です。課題が確認できれば、自社の強みを活かした効果的な提案をするのに役立ちます。
【設備の状況】では、研究開発を積極的に行っているか、特定の設備に大規模な投資計画があるかを確認しましょう。どんな分野を拡大しようとしているか把握すれば、ビジネスのチャンスや提案のタイミングを見極められます。将来の投資を検討しているかも重要なポイントです。
有価証券報告書ってどこにあるの?

有価証券報告書を確認する方法は次の2つです。
- 企業のIRページを確認する
- EDINET(有価証券報告書等の電子開示システム)を利用する
企業のIRページを確認する
上場企業であれば、ほとんどの企業が自社のサイトで有価証券報告書を公開しています。企業のコーポレートサイトにある株主・投資家情報やIR情報、IR資料室といったページで閲覧できます。GoogleやYahooなどの検索エンジンで「企業名 IR」と検索しても閲覧が可能です。
EDINET(有価証券報告書等の電子開示システム)を利用する
EDINETとは金融庁が運営する有価証券報告書の電子開示システムです。書類簡易検索画面から、調べたい企業の社名や証券コードを入力して検索できます。システムの利用は無料で、登録も不要です。EDINETでは有価証券報告書以外にも、半期報告書、四半期報告書などの書類種別を選択して検索できます。
まとめ:有価証券報告書は全部読まなくてもOK!

ページ数が多く、読むことに抵抗がある有価証券報告書ですが、すべて読む必要はありません。大切なのは有価証券報告書を読む前に、自分の知りたい情報を確認することです。見るべきポイントが分かれば、難解に思える有価証券報告書を攻略したも同然です。
多くの人は有価証券報告書のページ数に圧倒されて、中身を読もうとしません。この記事で解説した重要箇所を読むだけでライバルより深い知識を持った状態で投資や就活、営業活動をこなせるようになります。
情報は最強の武器です。知識を自信に変えて、一歩を踏み出しましょう。
この記事を書いた人
かずとし
WEBフリーライター
三重県在住、2児の父親。東証プライム上場企業に10年以上在籍し、現役でビジネスの第一線に立つ副業Webライター。
趣味は投資とマラソン。1,000万円超の投資経験(含み益300万円以上)と本業の知 見を武器に情報発信している。金融記事を主軸に、幅広いジャンルの執筆に対応。
もっと学びたい方へ|割引クーポンプレゼント!
感想をお寄せくださった方全員に、N-Academy「初心者でも簡単にマスターできる有価証券報告書の読み方」講座の10%割引クーポンプレゼント実施中。
クーポン対象講座
編集者情報
 |
株式会社デジタル・ナレッジ サービス推進事業部 事業部長 野原 成幸 |
| わからないことはインターネットで検索していた時代から、AIに質問することでさらにスピーディーに解決できる時代になりました。多くの場合、解決して終わりだと思いますが、「これについてもっと知りたいな」「学んでみたいな」ということも少なからずあるのではないでしょうか。 Pre.STUDYでは、何かを学びたいと思って検索する人にとっての学びの予習(prestudy)になり、明日誰かに話したくなる情報を発信しています。それと同時に、なんとなく湧いた疑問を検索した先で、ふと芽生えた知的好奇心をくすぐり、学びのきっかけになるメディアを目指しています。 | |